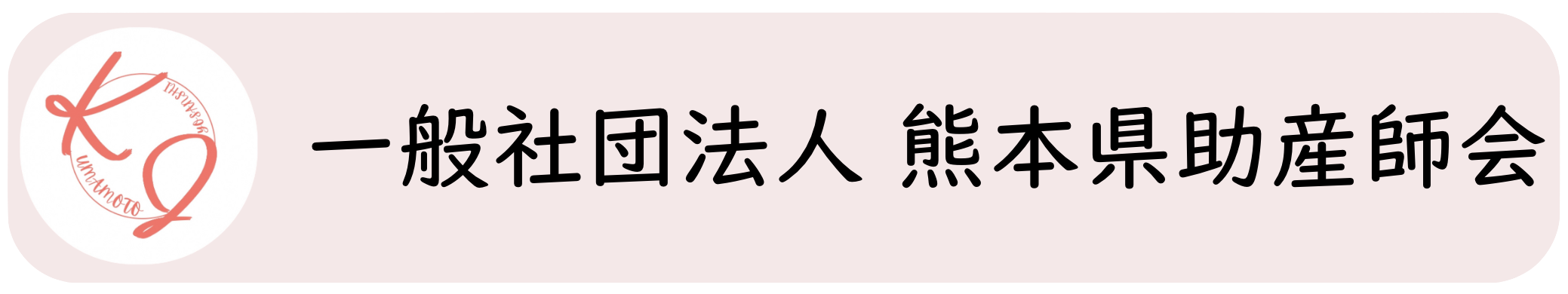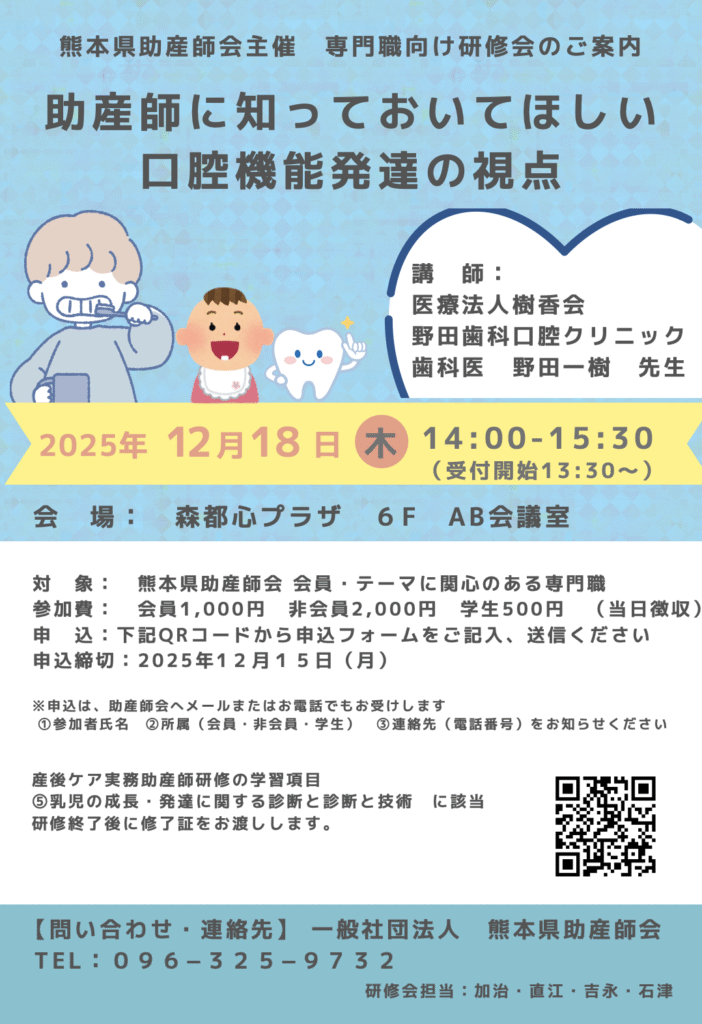ご案内
本研修を通して、参加者それぞれの立場で、女性の自立を促す助産師と女性のパートナーシップについて考えてみませんか。
今、妊娠・出産・子育てに関して、大きな変化が起こっています。分娩施設は集約化され、産後ケア事業はすべての母子に提供される事となりました。地域で開業する助産師の力が必要とされています。
今回、本研修会を熊本県助産師会で担当するにあたって、妊娠出産子育ての変化が、助産師に自立を求めていることに着目し、女性とのパートナーシップを考えていくチャンスだと捉えました。産む人の声に耳を傾け、声にできない母の声を拾い、寄り添っていく助産師の役割を一緒に考えましょう。
ご挨拶
会長挨拶
一般社団法人熊本県助産師会
会長 坂梨京子
パートナーとしての助産師
助産師の自立は女性の自律の第一歩
ソフロロジー(Sophrology)とは「調和した精神の研究」の意で、ギリシャ語の「sos」(調和)と「phren」(精神)、学問を意味する接尾辞-logyを組み合わせた造語です。松永昭先生が、フランスからこの学問を分娩の産痛緩和に応用実践しソフロロジー式分娩法として発展普及されました。子宮口7~8㎝開大の産婦さんが、分娩台の上で静かに深い呼吸をされ、「子宮の収縮はあるが、我慢できない痛みではない」と穏やかな表情をされていた。この方が、痛みに鈍感なわけではなく、子宮の収縮を赤ちゃんに会える力と、産前から継続ケアをする助産師の支援を受け、陣痛の痛みによる不安が解消され、緊張が解け、お腹の赤ちゃんと出産という共同作業を行われているのです。以前、熊本県母性衛生雑誌の取材でお話を伺ったときに、松永先生は「ソフロロジー法とは、単に分娩方法ではないのです。処世術なのです。」と「女性のその後の生き方にも関わってきます。」と続けられた。その言葉を聞き、松永先生から助産師へのメッセージであったことが、私の助産師教育の原点となっています。
分娩とは帝王切開も含めて、産前から、出産を経て産後、子育てへと寄り添って女性を寄り添い、女性の力を信じ、後ろからそっと支える助産師のケアは、対象となる女性との共同作業ではないかと思うのです。批判、比較、評価をしない、「あなたと赤ちゃんの生きる力を信じて支えていきます」と。もちろん、無痛分娩を産婦が選択された場合も例外ではないのです。
助産師学生と継続事例・産後3日目のお母さんの分娩の振り返りを行った時、お母さんが学生に「あなたが分娩の間ずっと一緒にいてくれて、とても心強く助かりました、ありがとう。」と言われ、学生は、「自分は十分なケアもできず、ただそばに付き添っている事しかできなかった」と目を潤ませていました。学生は分娩の経過中、自分の不安や、長く続く産婦さんの苦痛の場に居続けること、自分の無力感から、分娩室から逃げ出したかったのかもしれません。お母さんの言葉から、学生は助産師とは何かという根っこを学んだと思いました。
今回、熊本で九州沖縄地区研修会を開催するにあたり、助産師は女性のパートナーとして女性のリプロダクションを含めた女性の一生の健康に寄り添っていく者なのです。社会の変化は、女性の生き方、価値観にも大きな影響を及ぼしています。生きにくくなっているのかもしれません。私たち助産師は、その女性に、「こうしなければならないと」上から指示する者であってはならないのです。常にパートナーとなって共に歩いていけるように。この研修会で学びを深めることができましたら幸いです。
会長挨拶
一般社団法人熊本県助産師会
会長 坂梨京子
パートナーとしての助産師
助産師の自立は女性の自律の第一歩
ソフロロジー(Sophrology)とは「調和した精神の研究」の意で、ギリシャ語の「sos」(調和)と「phren」(精神)、学問を意味する接尾辞-logyを組み合わせた造語です。松永昭先生が、フランスからこの学問を分娩の産痛緩和に応用実践しソフロロジー式分娩法として発展普及されました。子宮口7~8㎝開大の産婦さんが、分娩台の上で静かに深い呼吸をされ、「子宮の収縮はあるが、我慢できない痛みではない」と穏やかな表情をされていた。この方が、痛みに鈍感なわけではなく、子宮の収縮を赤ちゃんに会える力と、産前から継続ケアをする助産師の支援を受け、陣痛の痛みによる不安が解消され、緊張が解け、お腹の赤ちゃんと出産という共同作業を行われているのです。以前、熊本県母性衛生雑誌の取材でお話を伺ったときに、松永先生は「ソフロロジー法とは、単に分娩方法ではないのです。処世術なのです。」と「女性のその後の生き方にも関わってきます。」と続けられた。その言葉を聞き、松永先生から助産師へのメッセージであったことが、私の助産師教育の原点となっています。
分娩とは帝王切開も含めて、産前から、出産を経て産後、子育てへと寄り添って女性を寄り添い、女性の力を信じ、後ろからそっと支える助産師のケアは、対象となる女性との共同作業ではないかと思うのです。批判、比較、評価をしない、「あなたと赤ちゃんの生きる力を信じて支えていきます」と。もちろん、無痛分娩を産婦が選択された場合も例外ではないのです。
助産師学生と継続事例・産後3日目のお母さんの分娩の振り返りを行った時、お母さんが学生に「あなたが分娩の間ずっと一緒にいてくれて、とても心強く助かりました、ありがとう。」と言われ、学生は、「自分は十分なケアもできず、ただそばに付き添っている事しかできなかった」と目を潤ませていました。学生は分娩の経過中、自分の不安や、長く続く産婦さんの苦痛の場に居続けること、自分の無力感から、分娩室から逃げ出したかったのかもしれません。お母さんの言葉から、学生は助産師とは何かという根っこを学んだと思いました。
今回、熊本で九州沖縄地区研修会を開催するにあたり、助産師は女性のパートナーとして女性のリプロダクションを含めた女性の一生の健康に寄り添っていく者なのです。社会の変化は、女性の生き方、価値観にも大きな影響を及ぼしています。生きにくくなっているのかもしれません。私たち助産師は、その女性に、「こうしなければならないと」上から指示する者であってはならないのです。常にパートナーとなって共に歩いていけるように。この研修会で学びを深めることができましたら幸いです。
※対象となる研修のラベルについて
選:アドバンス助産師認証制度選択研修
産:産後ケア実務助産師研修
開:開業助産師ラダーI制度
2025年地区研修会会長講演にあたって − 日本助産師会の活動指針と助産師の活動に関連する政策等の動き −
講師:髙田 昌代
対象研修:
選
産
開
女性と助産師のパートナーシップ
講師:ドーリング景子
対象研修:
選
産
開
産む力・生まれる力・自発から始まる生きる力
講師:齋藤 麻紀子
対象研修:
選
産
周産期のメンタルヘルスと乳幼児のアタッチメント形成
講師:吉田 敬子
対象研修:
選
産
開
無痛分娩の管理について
講師:福田 曜子
対象研修:
選
開
無痛分娩の助産師のケアについて
講師:小屋敷 明須香
対象研修:
選
開
Zoom入室開始(8:30~)
開会式(8:45~8:50)
※対象となる研修のラベルについて
選:アドバンス助産師認証制度選択研修
産:産後ケア実務助産師研修
開:開業助産師ラダーI制度
日本助産師会 会長講演(8:50~9:50)
演題:2025年地区研修会会長講演にあたって – 日本助産師会の活動指針と助産師の活動に関連する政策等の動き –
講師:髙田 昌代
所属:公益社団法人 日本助産師会 会長
対象研修:
選
産
開
女性と助産師のパートナーシップ(10:00~11:30)
講師:ドーリング景子
所属:和歌山県立医科大学 保健看護学部 保健看護学科 母性看護学准教授
対象研修:
選
産
開
産む力・生まれる力・自発から始まる生きる力(11:30~12:30)
講師:齋藤 麻紀子
所属:NPO法人Umiのいえ 代表理事
対象研修:
選
産
休憩(~13:00)
3部会集会(13:00~13:30)
内容:zoom会場を3つに分けて、オンライン集会を開催
周産期のメンタルヘルスと乳幼児のアタッチメント形成(13:40~15:10)
講師:吉田 敬子
所属:医療法人 コミュノテ風と虹メンタルクリニックあいりす 院長
対象研修:
選
産
開
無痛分娩の管理について(15:20~16:20)
講師:福田 曜子
所属:社会医療法人愛育会 福田病院 副病院長
対象研修:
選
開
無痛分娩の助産師のケアについて(16:20~17:20)
講師:小屋敷 明須香
所属:社会医療法人愛育会 福田病院 LDR師長
対象研修:
選
開
閉会式(~17:30)
オンデマンドお申込み
申込方法:
日本助産師会HP マイページからお申し込みください
申込期間:
今和7年10月26日〜今和8年1月21日
※会員マイページ内の「当日オンライン用」からお申込の方は、後日オンデマンド配信をご視聴いただけます
参加費
| カテゴリー | 参加費 ※お申込はマイページからお願いします |
|---|
| 助産師会 会員 | 6,000円 |
| 非会員 | 8,000円 |
| 学 生 | 1,000円 |
オンデマンド配信
配信期間:
令和7年 11月 15日(土) 〜 令和8年 1月 31日(土)

お問い合わせ
事務局:一般社団法人熊本県助産師会
TEL:096-325-9432
メール: josanshi-kumamoto@bz04.plala.or.j.p